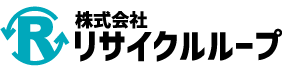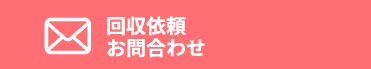なんでCドライブから始まるの?|Windowsの意外な歴史と理由を解説
タイトルとURLをコピーしました

Windowsでなぜ「Cドライブ」から始まるのか
パソコンを使っていると、WindowsのハードディスクやSSDが「Cドライブ」として認識されていることに気づきます。
さらに、USBメモリやDVDドライブが「Dドライブ」「Eドライブ」と続きますが、
「Aドライブ」や「Bドライブ」は最初から存在しないことがほとんどです。
では、なぜWindowsではCドライブから始まるのでしょうか?
歴史的背景:AとBはフロッピーディスク用だった
Windowsの基になったMS-DOS時代、
「Aドライブ」「Bドライブ」はフロッピーディスクドライブに割り当てられるのが一般的でした。
当時は外部記憶装置としてフロッピーディスクが主流で、
1台目のフロッピードライブをAドライブ、
2台目をBドライブとし、複数のフロッピーを使い分ける設計になっていました。
その後、ハードディスクが普及するにつれて、
ハードディスクには自動的に「Cドライブ」というラベルが付けられるようになりました。
現在でも残る伝統的な名残
現代のパソコンでは、ほとんどの人がフロッピードライブを使うことはなくなりましたが、
Windowsの「ドライブ文字割り当てルール」としてこの仕様が引き継がれています。
つまり、「A」「B」はフロッピードライブ用として予約され、
C以降のアルファベットがハードディスクや光学ドライブ、USBドライブに使われるのです。
Cドライブは「システムドライブ」としての役割も
多くのWindowsパソコンでは、
「Cドライブ」はWindowsがインストールされているシステムドライブとしての位置付けがあります。
アプリケーションや設定ファイル、
ユーザーファイルも初期状態ではCドライブに保存されるため、
「Cドライブ=パソコンの心臓部」というイメージが定着しています。
まとめ
「なんでCドライブから始まるの?」という疑問の答えは、
MS-DOS時代のフロッピーディスクドライブの名残にあります。
AとBは昔の名残として予約されており、
Cドライブから現在のハードディスクやSSDが始まっているのです。
このような歴史的背景を知ると、
普段何気なく使っている「Cドライブ」の意味がちょっと面白く感じられるのではないでしょうか。